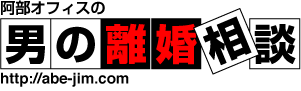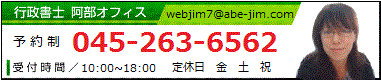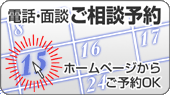面会交流とは、一緒に住んでいない親と子の交流のことです。子どもは離れて暮らす親と会う権利を持っており、子どもの権利条約でも確認されています。また、面会交流は、親の権利でもあり、親の義務でもあります。
面会交流の条件は、離婚協議書に記載するなど、書面にしておくことが重要です。
面会交流の条項には、協議型と執行型があります。子どもの年齢や配偶者との関係により選択します。
一般的に多いのは、協議型であり、面接することができるとして、日時、場所、回数等は協議して決めるという条項です。
執行型は、面接をさせるとして、以下のような条件を具体的に細かく決めるものです。参考:面会条件を詳細に定めた条項
決め方がよくわからない、話がまとまらないなどの場合には、お気軽にご相談下さいね。
家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
申立てをする家庭裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
参考:大阪高 平22(ラ)584号 平22.7.23決定 変更(確定) 原審 京都家
原審判(平成22年4月27日)の要旨の一部抜粋
子と非監護親との面会交流が制限されるのは、面会交流することが子の福祉を害すると認められる場合に限られる。
申立人が相手方や未成年者に暴力を振るっていたことは認められず、その他、申立人が未成年者と面会交流することが不適切であるとの事情はまったく認められない。
離婚による子の喪失感や不安定な心理的状況を回復させ、子の健全な成長を図るためにもできるだけ別居後早期に非監護親(非親権親)との面会交流を実施することが重要である。
面会交流を実施することによって子が情緒的不安定や不適応な症状を呈することも予想されるが、これらは一過性のものと考えられる。
面会交流の調停や審判が成立したのに、履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、履行勧告事件として立件し、通常、家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
家裁調査官の調査により、正当な理由なく、履行がされていない場合には履行勧告されます。
家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。
面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。
間接強制は将来に向かって効力がありますので、認められれば面会交流の違約金という位置づけが可能であり、履行確保の強いカードとなります。
間接強制が認められるためには、審判の文言が重要となります。
「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができると最高裁が判示しました。
間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
民法766条が改正(平成24年4月1日施行)され、面会交流が明文化されました。このことにより、面会交流はすべきものであるという前提が確立されました。従前は、離婚による親同志の葛藤や子の奪い合いの果てに、面会交流が拒否されて親子の引き離しが起きることがありました。
しかし、面会交流の義務が法律に明文化されたことで、面会交流の拒否によって親権者変更が認められた判例も出てきました。この判例によって、親子の引き離しに対応する手段ができたことになります。
一般に子どもは、両親との接触をもちながら育つ権利があるとされています。
子どもは、親の愛情を感じる事によって、安心して外の世界へ向かっていけます。
個人差はあるでしょうが、満たされなかった思いは大人になっても消えることはありません。
会えない場合、会わせられない場合には、監護している親が、子どもが愛情に包まれていると感じられるように努力して欲しいと思います。
決して、相手の悪口を子どもに言わないでほしい。
そうすることで、あなたの気持ちは晴れても、子どもは、自分が悪く言われたように感じてしまいます。
面会交流の条件は、離婚協議書に記載するなど、書面にしておくことが重要です。
面会交流の条項には、協議型と執行型があります。子どもの年齢や配偶者との関係により選択します。
一般的に多いのは、協議型であり、面接することができるとして、日時、場所、回数等は協議して決めるという条項です。
執行型は、面接をさせるとして、以下のような条件を具体的に細かく決めるものです。参考:面会条件を詳細に定めた条項
・月に何回
・何時間
・何日
・宿泊してよいのか
・会う場所はどうするのか
・会う日時は誰が決めるのか
・電話や手紙のやり取りを認めるのか
・どんな会わせ方をするのか
・子どもの受け渡しの方法
・連絡方法
等々。
・何時間
・何日
・宿泊してよいのか
・会う場所はどうするのか
・会う日時は誰が決めるのか
・電話や手紙のやり取りを認めるのか
・どんな会わせ方をするのか
・子どもの受け渡しの方法
・連絡方法
等々。
家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
申立てをする家庭裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
参考:大阪高 平22(ラ)584号 平22.7.23決定 変更(確定) 原審 京都家
原審判(平成22年4月27日)の要旨の一部抜粋
子と非監護親との面会交流が制限されるのは、面会交流することが子の福祉を害すると認められる場合に限られる。
申立人が相手方や未成年者に暴力を振るっていたことは認められず、その他、申立人が未成年者と面会交流することが不適切であるとの事情はまったく認められない。
離婚による子の喪失感や不安定な心理的状況を回復させ、子の健全な成長を図るためにもできるだけ別居後早期に非監護親(非親権親)との面会交流を実施することが重要である。
面会交流を実施することによって子が情緒的不安定や不適応な症状を呈することも予想されるが、これらは一過性のものと考えられる。
面会交流の調停や審判が成立したのに、履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、履行勧告事件として立件し、通常、家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
家裁調査官の調査により、正当な理由なく、履行がされていない場合には履行勧告されます。
家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。
面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。
間接強制は将来に向かって効力がありますので、認められれば面会交流の違約金という位置づけが可能であり、履行確保の強いカードとなります。
間接強制が認められるためには、審判の文言が重要となります。
「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができると最高裁が判示しました。
間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
民法766条が改正(平成24年4月1日施行)され、面会交流が明文化されました。このことにより、面会交流はすべきものであるという前提が確立されました。従前は、離婚による親同志の葛藤や子の奪い合いの果てに、面会交流が拒否されて親子の引き離しが起きることがありました。
しかし、面会交流の義務が法律に明文化されたことで、面会交流の拒否によって親権者変更が認められた判例も出てきました。この判例によって、親子の引き離しに対応する手段ができたことになります。
一般に子どもは、両親との接触をもちながら育つ権利があるとされています。
子どもは、親の愛情を感じる事によって、安心して外の世界へ向かっていけます。
個人差はあるでしょうが、満たされなかった思いは大人になっても消えることはありません。
会えない場合、会わせられない場合には、監護している親が、子どもが愛情に包まれていると感じられるように努力して欲しいと思います。
決して、相手の悪口を子どもに言わないでほしい。
そうすることで、あなたの気持ちは晴れても、子どもは、自分が悪く言われたように感じてしまいます。
- ■お客様の声
- 別居22年の形骸化した夫婦の離婚・18年間の子どもとの引き離し(63歳男性)
- 面会拒否と離婚交渉(44歳・男性)
- 出産後、妻が豹変(神奈川県・32歳・男性)
- 偽DV・面接拒否・高額な慰藉料請求(神奈川県・33歳・男性)
- 親権者からの相談・面接交渉権・お客様の声(東京都・33歳・男性)
- 偽DVで悩まれている方へ
- ■コラム
- 面会交流のしおり(名古屋家裁)
- 韓国の養育手帳
- 面会交流を禁止・制限すべき事由とは
- 親の紛争が子どもの発達に与える影響
- 柔軟性や理解力を欠く親【調査官が調査をしない事例】
- 別居後自宅の鍵を替えられて不安になった子ども【調査官が調査をする事例】
- 子の深刻な状況に気づかない親【調査官が調査をする事例】
- 兄弟分離【調査官が調査をする事例】
- 双極性障害の妻【調査官が調査をする事例】
- 面会交流の意義
- 親権争いになるケース
- 父の暴力に複雑な思いを抱く小4と小2の兄弟
- 境界性人格障害の母と発達障害の小3男児
- 面会交流支援
- 国際離婚と連れ去り大国
- 養育費で面会強要
- 親権と偽DV
- 目の前親が奪い合い
- 母の影響を強く受けた小5男児
- 主たる監護者と離別した3歳女児
- ステップファミリー
- びじっとの取材歴
- 離婚と親権〜子どもが希望したとき〜
- 民法改正〜面会交流〜
- 離婚と子ども(4)思春期
- 離婚と子ども(3)9歳〜12歳
- 離婚と子ども(2)5〜8歳
- 離婚と子ども(1)就学前
- 私のお父さん(10年目の再会)
- 子の監護に関する処分
- 離婚・子ども・BPD
- 面接交渉について
- 思春期の子育て
- ハーグ条約
- 面接交渉調停を考えている方へ
- ブラジルの共同保護法案
- 片親引き離し症候群
- 宇宙戦争にみる離婚後の面接交渉
- 北海道親殺し事件と離婚
- 子どもの奪い合い
- 子どもの親権及び監護に関する実態調査及び研究
- ■離婚問題Q&A
- 面会交流の中断を考え直してみませんか
- 別れた父親の探し方
- 娘に会いたい
- 離婚後の面接交渉の取り決め
- ■面会交流の判例
- 2020裁判例索引(面会交流の間接強制)
- 2020裁判例索引(面会交流)
- 第三者機関利用の面会交流条件を詳細に定めた抗告事件
- 面会交流の間接強制 15歳の子ども
- フレンドリーペアレントルールが採用された松戸の判決
- 面会交流不履行で父親に親権者変更(福岡家裁)
- 面会交流は教育の一環か
- 間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
- 養護施設に入所中の子と父の面会交流
- 「子どもが面会を拒否している」という主張
- 監護の割合によって婚姻費用算定表を修正した判例
- 面会交流拒否の損害賠償請求
- 面会条件を詳細に決めた条項
- 子どもが父に対して持つ複雑な感情
- 矛盾を含みながらも子どもが親を完全拒絶
- 面接交渉不履行1回5万円の間接強制岡山家津山支平20.9.18(決)
- 未成年者の心情の成長にとって重要であるとして、抗告人との直接の面接交渉を認めた事例(大阪高 平21.1.16(決))
- 面接交渉が実現しないので3歳の子を保育園から連れ去った事例
(東京高 平20.12.18(決)) - 精神疾患・児童相談所が介入していたケース
- 元配偶者への強い執着と面会交流
- 子の福祉を害する恐れが高いとして面接交渉を却下した事例
- 3名の子の内1名の面接交渉を認め、その妨害を禁止した事例
- 親権者の再婚による事情変更
- 面接交渉が否定された事例
- 面接交渉を定めた調停条項を変更し面接交渉を全面的に禁止
- 面接交渉の実地に第三者を介在させることを命じた事例
- 未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否
- ■資料
- 子の返還手続き要綱(ハーグ条約)
- 面会交流のリーフレット