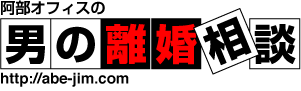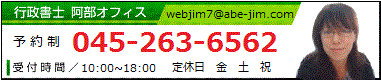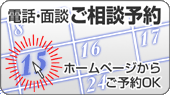離婚を考えたときに、問題になるのが、財産分与です。
財産分与の範囲はどこまでなのか、ローン中の住宅はどうすればよいのか、など、今後の生活にもかかわってきますので、慎重に決めましょう。
財産分与が決まったら、離婚協議書に記載しておくことで、後のトラブルを回避することができます。
財産分与には、3つの要素があります。
財産分与は夫婦で築いた財産の分与ですから有責配偶者でも財産分与は請求できます。まれに財産が多い方の場合に慰謝料よりも財産分与の額の方が多くなるケースもあります。
借金も財産分与の対象になることがあります。
日常家事債務に該当する場合等は分与されます。たとえば、住宅ローンや子どもの教育ローンなど、夫婦で分与します。
財産分与の除斥期間は2年です。
感情にまかせてなにも決めずに離婚してしまい請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。
離婚届けを提出するのは、すべて決めてからにしましょう。
不動産の財産分与をする場合には、2つのパターンがあります。
1の場合に問題となるのは、不動産の名義です。 特にローン中の場合には、名義変更ができないなどという問題が生じます。
期間を決めて、賃借権を設定するといった事例もあります。
売却の金額がローン残額に満たないため、住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んでいらっしゃる夫婦も多く、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。
連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。(連帯債務とは、夫婦間の契約ではなく、連帯債務者と金融機関の契約です。)
ローン付不動産の処分方法及びローンに関しては、個別具体的な対応が必要となります。
当オフィスでは、不動産アドバイザーの知恵を借り、解決方法を提案させていただきます。 この場合、メール相談では、対応しきれませんので、ローン契約書や登記簿謄本等をお持ちいただき、面談相談にてお願いいたします。 財産分与を原因として、不動産を配偶者に譲渡した場合、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。
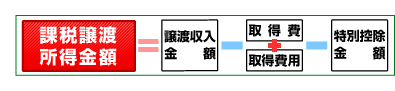
また、取得費や譲渡費用など、細かな決まりがあるので、税務署で確認することが必要です。財産分与として、すっかり渡してしまった後で、多額の税金が課せられてしまったなどということがあっては、泣くに泣けません。 特別控除マイホームの場合は、居住用財産を売却した場合の3千万円控除が受けられますが、これは、離婚後の財産分与である必要があります。
財産分与の範囲はどこまでなのか、ローン中の住宅はどうすればよいのか、など、今後の生活にもかかわってきますので、慎重に決めましょう。
財産分与が決まったら、離婚協議書に記載しておくことで、後のトラブルを回避することができます。
財産分与には、3つの要素があります。
1. 婚姻中に築いた夫婦の共通財産の精算
この共通財産とは、その財産の名義で判断をするわけではありません。
大きくわけると、金銭(預貯金等含む)・不動産・動産・です。細かいところでは、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。
清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから、別居する時点までの財産とされています。
大きくわけると、金銭(預貯金等含む)・不動産・動産・です。細かいところでは、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。
清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから、別居する時点までの財産とされています。
2. 離婚後の扶養給付
なぜ、離婚後に扶養するのか?と思われる方も多いでしょうが、その理由としては、「一度は夫婦であったのだから離婚後も扶養すべき」「離婚後に生活に困れば生活保護を受ける可能性が高くなるため(この資源である税金は、国民が払っているものだから、離婚の負担を無関係な国民に負わせてしまう)」などと言われてきました。
しかし、少々時代にそぐわないことと、説得力に欠けている感はあります。
最近では、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。
この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで、財産分与する側の余力があることが前提で、分与を受ける側が、高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護するか、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。
しかし、少々時代にそぐわないことと、説得力に欠けている感はあります。
最近では、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。
この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで、財産分与する側の余力があることが前提で、分与を受ける側が、高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護するか、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。
3. 離婚慰謝料
最高裁は、慰謝料も含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。
学説においては、財産分与を清算および扶養に限定しつつ、できるかぎり紛争を1回で解決するために慰謝料を含むものとする包括的な取扱いも認めるという柔軟かつ実践的な解決を図ったと理解されています。
しかし、慰謝料を含めて財産分与をしたと思っていたところ、後から慰謝料も請求されたなどということがないように、項目をわけて離婚協議書を作成したほうが安心です。
学説においては、財産分与を清算および扶養に限定しつつ、できるかぎり紛争を1回で解決するために慰謝料を含むものとする包括的な取扱いも認めるという柔軟かつ実践的な解決を図ったと理解されています。
しかし、慰謝料を含めて財産分与をしたと思っていたところ、後から慰謝料も請求されたなどということがないように、項目をわけて離婚協議書を作成したほうが安心です。
借金も財産分与の対象になることがあります。
日常家事債務に該当する場合等は分与されます。たとえば、住宅ローンや子どもの教育ローンなど、夫婦で分与します。
財産分与の除斥期間は2年です。
感情にまかせてなにも決めずに離婚してしまい請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。
離婚届けを提出するのは、すべて決めてからにしましょう。
不動産の財産分与をする場合には、2つのパターンがあります。
- どちらかが住み続ける場合
- 売却する場合
売却の金額がローン残額に満たないため、住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んでいらっしゃる夫婦も多く、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。
連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。(連帯債務とは、夫婦間の契約ではなく、連帯債務者と金融機関の契約です。)
ローン付不動産の処分方法及びローンに関しては、個別具体的な対応が必要となります。
当オフィスでは、不動産アドバイザーの知恵を借り、解決方法を提案させていただきます。 この場合、メール相談では、対応しきれませんので、ローン契約書や登記簿謄本等をお持ちいただき、面談相談にてお願いいたします。 財産分与を原因として、不動産を配偶者に譲渡した場合、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。
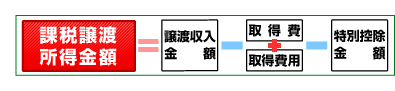
また、取得費や譲渡費用など、細かな決まりがあるので、税務署で確認することが必要です。財産分与として、すっかり渡してしまった後で、多額の税金が課せられてしまったなどということがあっては、泣くに泣けません。 特別控除マイホームの場合は、居住用財産を売却した場合の3千万円控除が受けられますが、これは、離婚後の財産分与である必要があります。
■離婚問題Q&A
- ローン付2世帯住宅がある場合
- 不動産の頭金に充当した相続財産
- 負の財産分与(住宅ローン)
- 離婚条件のすすめかた
- 子どもの姓と戸籍の関係
- オーバーローン不動産の財産分与
- 離婚に伴う家の名義問題について
- 個人年金は共有財産?
- 共有名義で連帯保証人での離婚、夫が財産放棄
- 夫名義のローン付マンションを妻に財産分与
- 2世帯住宅のローン
- 自宅の名義変更について
- 離婚の際の親権と財産分与について
- 離婚に伴う家の名義変更
- 公正証書の作成
- 財産分与の除斥期間
- 離婚と財産分与、家屋
- 共有名義ローン付住宅の財産分与
- H19年4月前の離婚での財産分与(年金)
- ■財産分与の判例
- 2020裁判例索引(離婚・財産分与)
- 宝くじ当選金は財産分与の対象
- 離婚後に不動産が共有物件とされた判例
- 夫婦間贈与と財産分与の関係
- 将来の退職金と財産分与
- 算定表より多く支払った婚姻費用は財産分与の前渡し?
- 扶養的財産分与として使用賃借権を設定した事例
- 配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性
- ■離婚の資料