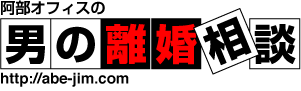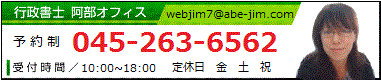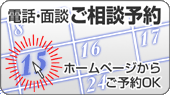お客様の声>父親が4歳の子の親権者となった経験談(37歳男性)>経験談:監護者指定審判
※阿部オフィスに寄せられたお客様の声の経験談です。作成者は37歳男性です。
経験談:監護者指定審判(37歳男性)
1.審判の影響力
審判の影響力は裁判の判決にも大きく影響を与えます。
監護者の指定が審判で確定すると、余程の事が無い限り親権もほぼ決定してしまいます。
この「余程」という言葉が曖昧な定義ですが、おそらく監護者指定を受けた者の死や犯罪をし逮捕された、監護している子供に著しい変化があった等だと私は思います。
結論、審判が下るとその後の裁判では結果を変えることは難しいということです。
審判が下ると即時抗告申立期間があり、即時抗告がなされると高等裁判所での抗告審へと移行されます。
即時抗告の結果、原審と結果に変更がなく、決定されてしまうとそれはもはや「高裁決定」となり、その後、離婚裁判する家裁は高裁と比べると下位になるため、家裁では「高裁の結果」を覆すことがほぼ不可能だからです。
離婚裁判判決の親権者選定内容を不服として上告したとしても、次に争う裁判所は高裁ですので、審判決定を出した高裁と同じ階級であるため、ここにおいても覆すことが困難です。
ですので、この審判で必ず結果を出さないといけません。
この審判で成果を出さなければ後はありません。心して取り掛かって下さい。
2.審判の状況
調停を経験されている方ならご存知だと思いますが、審判を行う場所は5〜6人くらいは入れる会議室のような部屋で行われます。
ミーティングルームくらいの広さです。非公式の場です。
傍聴人は居ません。
テーブルの前に左から調査官、審判官(裁判官)、書記官が着座し、私の隣には相手方(元妻・元妻の弁護士)が着座していました。
裁判とは違い、調停のように思えますが、性質が全くことなります。
まず、発言することは全て証言とみなされ、議事が取られています。
審判官からされる審問は裁判で云う尋問にあたります。
進行は、事前に提出した準備書面と証拠に目を通した審判官から、書面に基づいた審問を受けます。
裁判とは違い、突発的に審問が申立人・相手方にされます。審問では一問一答です。
慣れていないと愚だ愚だと余計な事を話してしまい、肝心な審問への回答があやふやで終わってしまい審判官に意図が伝わりません。
特に初回の審判は緊張している状態ですので、冷静な回答はできないと思います。
ですので、【本人起訴を考えている方へ】が確実に出来ていないと、対応できません。
私の場合、審判は5回ほど行われました。
何回行うかはケースによって変わると思いますが、裁判より審判期間は圧倒的に短いと思います。
3.準備書面について
各地方裁判所のホームページに書式がアップロードされています。
申し立てるときは、申立書に必要事項を記載し、必須書類、準備書面と証拠になるものを一緒に提出します。
恐らく、最初に提出する準備書面は事件概要や経緯等を記載する必要があるので、相当長いものになると思います。
記載する内容は事実のみであり、独自見解や主観を込めても意味がありません。
証拠や基準を指し示す「定義」が必要です。
私も随分悩まされ、書き直しを繰り返しました。
本人が書くと当然主観が入ります。
これまでの常識にとらわれていることと先入観が作成の邪魔をします。
私は作成中に煮詰まった時は、パチンコやゲームをしたりと他の事を考え、頭を切り替えました。
最初の準備書面は3週間、慣れてくると1週間くらいで作成しました。
作成が終わると20回ほど読み返し、さらに1書面につき2〜3回ほど添削修正を繰り返して完成させ、完成したものをまた20回ほど見返し、裁判所に郵送して提出しました。
4.証拠について
自分の主張を裏付けるための必須アイテムです。
これがない主張は、愚痴同然です。
手元にある証拠はきちんと整理し、どの事実の証明に何の証拠を充てるかを見極めなければなりません。
また証拠を提出するタイミングも重要であり、きちんと戦略を立ててから提出しないと無意味な事を立証したり、時には相手側に有利なアイテムを与えてしまうことになり兼ねません。
私の場合、準備書面内の主張に関係の無い証拠の提出を控えました。
審問内で提出を求められた場合に備え、その関連の証拠の写しを準備していました。
効果的に証拠を使えたのは、相手が嘘の主張をした時でした。
ボクシングで云う、カウンターのような効果が得られます。
相手の主張を崩すだけでなく、相手が嘘をついていることを立証できます。
相手の主張のブレを引き出すチャンスになるかもしれません。
嘘は嘘を呼びます。
証拠を有効活用し、自分が有利になる展開に導いて下さい。
5.審問について
準備書面の作成時に何度も読み返した理由は、その後行われる審問に備えてのことです。
審判内では、準備書面に基づいた審問を受けます。
審問内容は主に、準備書面内の記載内容が審問に対する回答と合致しているかや準書書面内容の補足説明です。
審問に関しては弁護士が付いていても、ご自身で対応することになります。
この審問に曖昧な回答をすると準備書面内容に不信感を持たれます。
私の場合、準備書面を自分自身で作成していたので、審問に対してはあまり困ることはありませんでした。
6.調査官調査について
子供の心情や環境に配慮をしなければならない理由の一つに、家裁調査官の家庭訪問調査があります。
調査は、まず当事者との面談から始まります。
1時間程度。
調査官は2名。
場所は裁判所内の調査室で行われます。
事件概要やこれまでの子供との関わりについて細かく聞かれます。
私が受けた面談は、それほど堅苦しいものではなく、むしろ調査官に引き出されるようにすらすらと質問に対して回答したような気がします。
次に子供が通っていた保育園の調査でした。
これは、後に作成される調査官報告書を見ない限り、どのような調査をしていたかはわかりません。
調査官報告書には子供の保育園での状況や親の態度等、保育士らに調査した結果が記されていました。
最後に子供の居住地での家庭訪問です。
家族全員揃っている状態での面談、子供と調査官の面談、補助監護者と調査官と面談がありました。
3時間程度。
子供との面談は、子供に相当な配慮して面談していました。
調査内容の詳細は、各事例毎の争点が異なりますので、あえて詳細は記載しません。
これらを行った後、調査官報告書が作成されます。
報告書には、家庭内の家具の配置、子供と当事者の関係、補助監護者と子供との関係が詳細に記載されていました。
子供の表情まで記載されているくらいの細かさです。
プロである調査官調査に取り繕った環境は通用しません。
先に述べた通り、いち早く子供の安定した環境と親密な関係を築く以外、この調査を乗り切る方法はありません。
この調査は、裁判所の調査であり、裁判所の見解と言っても過言ではなく、裁判所が示す証拠に値しますので、この調査で結果が出せなければ、結果が見えてしまいます。
親権や監護者指定審判では、ほぼ実施されると思いますので、争いの前段から意識しても遅くないと思います。
調査後の調査官報告書の開示請求についてですが、本人で審判を対応されている方は、担当書記官に調査官報告書の仕上がり進捗を電話で確認し、仕上がり後、自身で裁判所に出向き、調査官報告書の写しを複写しなければなりません。
書記官に相談すると方法を教示してくれます。
複写は自分で行います。
書記官に証拠複写用のコピー室に案内されます。
全面ガラス張りで、監視されています。
証拠隠滅等の防止から、このような措置がとられていると思います。
書記官立会いの下、コピーをとります。
1枚10円、有料です。
コピー部数に制限はありませんが、事前に何部必要かは申請が必要です。
ミスプリントした場合、その場にてシュレッダー処分します。
7.審判について
書面や証拠、調査官の調査報告書が出揃い、事実関係がはっきりした頃に「審判」が下されます。
私の場合、審判内で審判官が審判内容を口頭で告げ、元妻に長女の監護者指定を取り下げるように促しましたが、元妻は審判官の方向性を否定し審判を望みました。
結果、1カ月後、裁判所より「審判文」が送られてきました。
その書面には、私が長女の監護者とはっきり記載があり審判官の発言通りでした。
「死ぬ気でやれば、やってやれないことはない」、このことを痛感しました。
紛争が始まり10ヶ月後の事でした。
8.即時抗告について
審判が出て喜んでいるのも束の間、高等裁判所より即時抗告が元妻からなされたとの通知がありました。
審判が下され、2週間以内に抗告期間があり、抗告がなされると次は高等裁判所での争いになります。
高裁と言えど、出廷するわけではなく、抗告状についての反論を淡々と書面に記載するだけです。
書類送付先が、家裁から高裁になっただけですが、審理する裁判官は、3人増えます。
裁判長1名、裁判官2名。
審判時点で確たる主張と証拠、さらに調査官報告書という証拠がついている状態でしたので、証拠は完璧に近い状態でした。
争点は家裁の審判の是非を問うものです。
この段階で逆転は不可能に限りなく近いです。
なぜならば、証拠の一部に調査官報告書があるからです。
調査官報告書は裁判所が行った調査であるため、それを否定すること自体が不可能であるからです。
そのような状況下の中、元妻の弁護士の争点がずれた主張のみの抗告状はもろく、元妻には事態を悪化させた結果で、高裁より私が長女の監護者である「決定」が通達されました。
即時抗告がなされ、3か月後の事です。
この即時抗告の「決定文」が私の新たな「証拠」となり、アイテムに付加されました。
9.審判の終わり
私が長女の監護者であることを高裁がはっきりと認めてくれました。
その後、元妻側は最高裁判所に抗告することもなく、私の監護者は「決定」から「確定」へと変わり、晴れて長女の監護者となりました。
長女の監護者になれたという喜びよりも、「長女の主張を貫き通した」、「裁判所に長女の意思が伝わった」ことへの喜びが大きかったかもしれません。