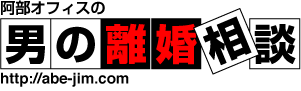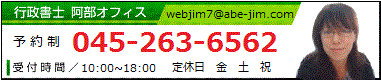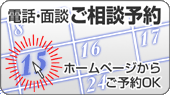お客様の声>父親が4歳の子の親権者となった経験談(37歳男性)>経験談:親権(監護権)の重要なポイント
※阿部オフィスに寄せられたお客様の声の経験談です。作成者は37歳男性です。
経験談:親権(監護権)の重要なポイント(37歳男性)
1.監護歴が大切
私自身、元妻と同居期間中は当然、元妻が主たる監護者でした。
審判中も当然、元妻側はそれを主張して取り戻そうとしてきました。
元妻側には、母子手帳や保育園の連絡帳等、子どもの監護歴を形として表す物証があります。
紛争当初より意識していたのが「とにかく監護歴」でした。
私には監護歴を証明する物がない状態です。
しかも、長女は私の実家に預けていましたが、その実家は私の居住地から遠く650kmも離れた場所。
どのように監護歴を作るか悩みました。
1ヶ月2回、勤務先に無理を言い夜行バスを利用して実家を往復し、長女の面倒を見ました。
保育園の送り向かい、食事、お風呂、添い寝等、長女にべったり状態です。
特に保育園には気を遣いました。
家庭環境の変化、保育園の転園により、長女の生活が完全にリセットした状態に加え、元妻との紛争状態もあり、第三者の意見を聞くことは重要であり、特に保育士の話に耳を傾けることは有効な手段でした。
私が居住地に戻った時は、スカイプのライブチャットを利用して長女とのコミュニケーションを図りました。
出歩くときも小型PCを持ち歩き、いつでも長女と顔を合わせられる環境を作りました。
このような状況をコツコツと積み重ね「監護歴」を形成していきました。
無から何も始まりません。だから、今やれることを精いっぱいやるだけです。
2.子供のより良い生活環境を迅速に整える
いち早く子供の心情を安定させる為に、環境作りは迅速に行って上げてください。
役所の手続き、保育園の入園、家庭環境等、整備しなければならないものはたくさんあります。
私の場合は偶然に近いようなものでしたが、実家に行った長女が近所の保育園に通いたいと言い出したので、即入園手続きを取りました。
紛争開始から1週間経過した頃くらいだったと思います。
元々、長女は私の実家が大好きだったので、馴染むことには時間が掛らず、保育園も手続きから2週間ほどで登園していました。
新たに長女が通いだした保育園は私も幼いころに通っており、保育士には私の同級生や私が通っていたころの保育士が居たため、馴染みが深く助かりました。
しかし、私が実家を訪れ、自分の居住地に戻る時、長女はよく泣いていました。
その負担を軽減するため、私は実家から居住地に戻るときは、会社に出勤する服装をし、「仕事に行ってくるね、また帰ってくるから。」と言い聞かせました。
それを繰り返していると子供が現状の生活に馴染み、「いってらっしゃい」とニコニコ笑いながら言うようになるほど、生活が安定しました。
3.子供の将来を壮大に語られるようなビジョンを立てる
裁判所での争いが始まると、当然今後の子供の監護や将来について尋ねられます。
ここで自分自身が、子を育て将来どうしていくかを話さなければなりません。
特に男性は仕事をしながら育児となると難しい回答です。
私は正直に「実家の両親や兄に協力してもらいながら監護を継続する。
近場には小学校・中学校もあり、私自身が通ったので縁も深い。
子供は今の環境に馴染み、今までの生活より充実しているので、子供の環境を変更するよりも自分が子供の環境に合わせる為に、紛争終了後に転職する」等、子供を今後どう育てるかを壮大に語り調停員や裁判官の心を動かすよう働きかけました。
子供の監護をできるかできないかを決めるのは、裁判所であり、当事者ではありません。
相手のことを否定するネタを探すよりも、自分の監護に対するビジョンをいち早く確立し、即実行して下さい。
余談ですが、私の元妻は私の悪口ばかりを言い続けた結果、裁判官より「自分のことを棚に上げて」的なことを審判文に書かれておりました。元妻には東大法学部出身の女性の弁護士が紛争当初より付いていました。
4.離婚と親権は必ず切り離して考えること
離婚は「夫婦男女間の問題」であり、親権とは全く関係ありません。
夫婦不仲で悪口を言い合うのは勝手です。
しかし夫婦の争いで、子供を担ぎ出し、悪口を言い合うことは大きな間違いです。
なぜならば、親権とは「子の福祉」つまり「子供の主張」をさすものであり、夫婦喧嘩の口実ではありません。
ここを誤解してしまうと、特に男性であれば、ほぼ女性に親権が渡ってしまいます。
親権争いは夫婦喧嘩の場でなく、離婚後の子供の将来を考える場です。
絶対に誤解しないで下さい。
私の事例でも、離婚と親権は個別に考えました。
私も当然人間であり、親権を求めるあまり、感情を優先してしまい、元妻のことを貶すような表現をしてしまいがちでした。
このような状況から抜け出すために行き着いたのが、親権での主張は「自分の監護状況の自慢」でした。
「自分はこんな環境を子供に準備した。子供はずっとここに居たいと言っている。」と子供の様子について詳細かつ丁寧に主張することにしました。
提出書面を読む裁判官が「この人なら安心!子供をこの環境から替えてはいけない!これが子供の主張だ!」と思わせる内容になるように、子供の細かな行動や成長、生活状況を記載するように心がけました。
また、文章にできない子供の表情については写真を添付しました。
離婚についての主張は、事実のみを淡々と書き綴りました。
「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」の通り、親権・監護者争いでは裁判所もあまり興味がもたないネタです。
結果論ですが、離婚に労力を費やするより、親権・監護者を重視したことが結果に結びついたと思います。
5.引き際を弁えること
引くべきところは引くことも肝心です。
状況を見定めるには情報が必要です。
メリット・デメリットを考え、判断を出すのは難しい事とは思いますが、よく状況を見定めて下さい。
引き際をうまく利用すれば、取引の好機に変わることもあります。
子供の親権を重視するなら、「肉を切らせて、骨を断つ」のような、多少の痛手は覚悟して下さい。
引いているばかりではただの泣き寝入りですので、冷静な判断とタイミングで引き際も結果を見据え、有利に利用して下さい。
6.判例や類似情報には目を通すこと
親権類の判例や事例を見ると、涙ぐましいものも多く、現状の自分を照らし合わせると耐えきれないと思いますが、現実から目を逸らさず、現状を把握する為に必ず過去の判例や類似情報には目を通して下さい。
私のように、ご自身で調停や審判を対応される方は必須です。
判例は試験の過去問と同じであり、争いの状況を目定める目安になります。
また、主張や判決にも過去の判例は取り入れられるので、紛争の落ちを見定めるには知っているべきだと思います。
「男性が親権」という考え方は過去の判例から考えると真向から対立する考え方ですので、親権争いは当然男性が圧倒的に不利です。
「不利からの逆転」の為の「逆転の発想」を考える上でも、これまで争った方々の体験談は私にとっては「知恵の財産」でした。
逆にやってはいけないことも掲載されています。
特にアンチな考えで争いに臨んだ方の体験談は「とってはならない行動の見本」として参考になりました。