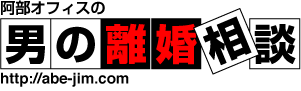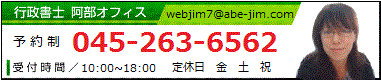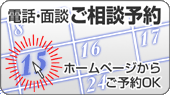監護態勢は、監護者の決定について大きな要素となります。
子育てをする上で当然に必要なことですが、監護者の決定においても、将来を見通した具体的で現実的な監護養育プランが必要なのです。
広島高決平19.1.22(家月59-8-39)
父親が母親に対して暴力を加えたために、母親が3歳と2歳の未成年者を残して別居し、その後、未成年者らの引渡しを求めた事案であるところ、
抗告審は、
「抗告人(母親)・相手方(父親)とも監護者として適性を欠くとまでいえず、(中略)物的な養育環境の面でも、抗告人・相手方とも未成年者らが安定して生活するに足りる住居や保育所などの環境を整えており、この面で両者に有意な差があるとはいえない。しかしながら、今後の未成年者らの人的な養育環境の面を考えると、抗告人は、当面は抗告人一人で現在の住居においてE(前夫との子)の外、未成年者らを養育し、いざというときには友人の援助も期待しているが、養育の意欲に欠ける点はないとしても、一人で未成年者らの監護を全うするのは現実的には困難であるという外なく、友人の援助なるものも具体性に乏しく、これを安易に期待することはできない。
また、抗告人は、いずれ○○へ転居して実家の母を監護補助者とし、その援助を受けることをも期待しているが、これまでの経緯に鑑みると、その現実的な可能性には疑問を差し挟まざるをえないし、その具体的な態様も明らかでない。
これに対し、相手方に関しては、現在の人的な養育環境に大きな変化のないまま、安定的に推移するであろうことが期待できる。」
とし、
「将来の人的な養育環境が不分明なまま現在の監護状況を変化させることはいたずらに監護の安定性を欠くことになるのであって、相手方の下で生活する方が、未成年者らの福祉に敵うというべきである。」
として、母親の申立てを却下した原審判を維持した。
家月63-9-21